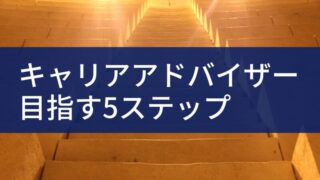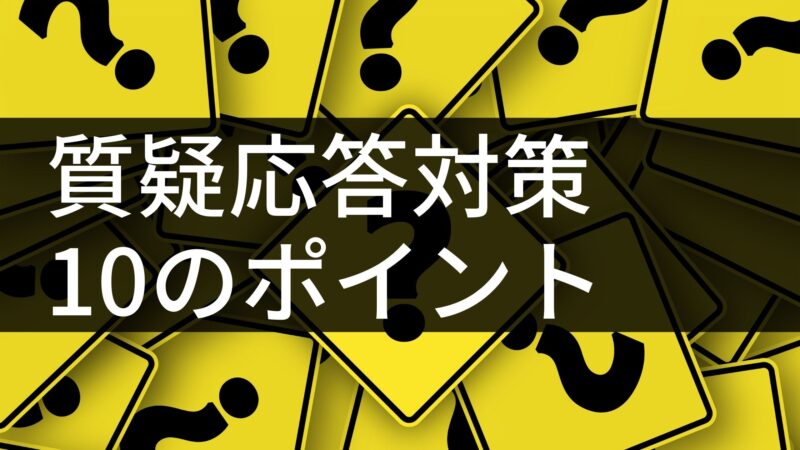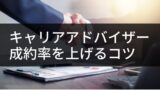キャリアアドバイザーあなたは、次のような悩みを抱えていませんか?

求職者からの「どんな質問をすればいいですか?」という相談に戸惑う

質疑応答って、アドバイスのし方がわからない

企業側からの質問への準備ができていない

次のような経験をもつ私(@taqnock)が、あなたの悩みに答えます
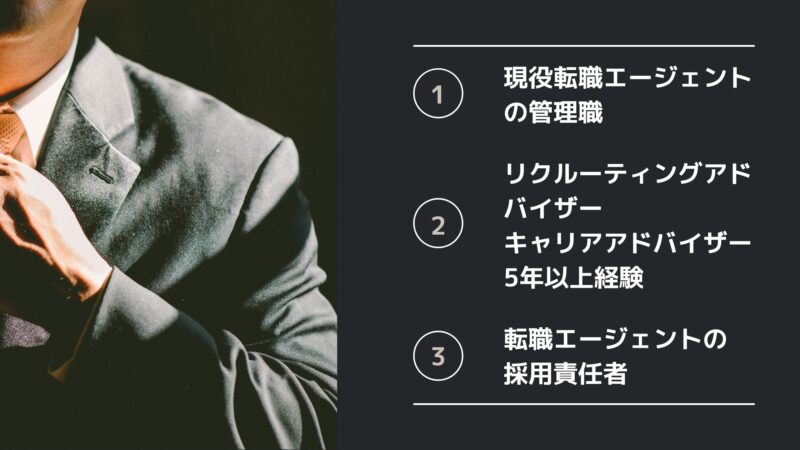
”質疑応答”って、企業ごと・求職者ごとでケースバイケースなので、正解がなくて難しいですよね?
そんな中、求職者からこんな質問をされると困ります…

どんな質問をしたらいいですか?
ただ、正解はありませんが、共通する失敗はあります。
失敗の共通点を押さえておくだけで、面接通過率を上げることができます。
この記事を最後まで読むと、面接通過率をあげるために面接対策で準備をすべき質疑応答の詳細が分かります。
- 企業からの質問への準備をする6つのポイント
- 求職者が質問を準備する4つのポイント
- 臨機応変なアドバイスができないときに確認すること
キャリアアドバイザーがすべき質疑応答対策の全体像

質疑応答の準備は、大きく次の2つのポイントに分かれます。
- 企業側から受ける質問
- 求職者側が準備する質問
それぞれ、解説していきます。
企業側から受ける質問にキャリアアドバイザーがアドバイスする6つのポイント

面接においては、面接官から多くの質問をされます。
中でも、特に気を付けるべきポイントを6つ紹介します。
- 【ポイント①】対の質問
- 【ポイント②】入社可能時期についての質問
- 【ポイント③】他社選考状況についての質問
- 【ポイント④】機密情報に触れる質問
- 【ポイント⑤】質問履歴の提供
- 【ポイント⑥】回答にはPREP法を使う
それぞれ解説していきます。
【ポイント①】対の質問
対の質問とは、例えば次のようなものです。
- 長所と短所
- 成功と失敗
- 自己評価と他者評価
対の質問に回答する際に意識すべきポイントは、次の2つです。
- 対の質問のうち、マイナス側のリカバリー方法
- マイナス度合い
なぜリカバリー方法が重要なのでしょうか。
それは、面接官は「マイナス要素そのもの」を確認したいわけではないからです。
求職者が「マイナス要素にどう向き合ったか」を確認したいからです。
マイナス度合いとは、「リカバリー説明ができないほどにマイナスな要素」は話してはいけないということです。
具体的には、次のような要素。
- ビジネスマナーに反するマイナス要素
- 組織で働くことに適さないマイナス要素
例を挙げると、次の通り。
- 時間を守れない
- 人とコミュニケーションが取れない
- 経営理念を無視する
模範的な回答の流れを解説すると下記のようになります。

あなたの長所と短所を教えてください

はい、長所は○○で、短所は●●です

では、●●の短所に対して、どのように対処していますか?

はい、私の●●という短所は、○○のようなシーンで問題になることを自覚しています。
ですので、事前に○○の準備をすることで可能な限り克服できるよう、努めています。
【ポイント②】入社可能時期についての質問
入社可能時期については、次の①~③にかかる期間を想定した上で答えましょう。
内定通知書発行
↓ ①
退職交渉
↓ ②
業務引継ぎ
↓ ③
入社
特に注意すべきなのが、以下の2つのケースです。
- 入社可能時期が短すぎるケース
- 入社可能時期にギャップが発生するケース
それぞれ、面接官の持つ印象を解説します。

もし入社して頂くとすると、いつ頃入社が可能ですか?

すぐに入社できます!
②~③の期間があまりに短い場合、採用担当者の次のような印象につながる可能性があります。

現職での業務引継ぎが雑だなぁ。
もしかしたら仕事に対して無責任な方なのかもしれないな…

もしかしたら無責任な辞め方する人なのかも…
求職者としては、求人先企業を優先したい一心で「すぐに入社できます」と答えてしまいがちです。
求職者の置かれた状況と伝える入社可能時期とのバランスが重要です。
次のような状況にある場合は、入社可能時期が短くても問題ありません。
- 現職の移転、倒産が決まっている
- 現職で希望退職、整理解雇がある
- 転居の必要がある状況
退職せざるを得ない状況です。
採用担当者側の視点でいえば、以下のようなコメントが出る理由であればOKということです。

その事情があるなら、致し方ないね…
~面接内~

すぐに入社できます!

では、社内状況を鑑みて入社時期の検討をさせて頂きますね
~内々定の段階~

採用の方向で検討を進めていますが、入社可能時期に変わりはありませんか?

やっぱり、できれば6か月後の入社を希望しています…

そうならそうと、早くいってよ…
というように、2つの時期の間にギャップが生じないよう注意が必要です。
- 面接内で回答した入社可能時期
- 内々定の段階で回答する入社可能時期
なぜなら、求人先企業の採用計画とのズレが出ることで、採否の結果が変わるからです。
採用担当者は「〇月までに〇人採用する」という採用計画を遂行するために動いています。

採用計画上〇月には採用完了していないとマズイんだよなぁ…

他の人で進めた方が計画通りにいくかもなぁ…
求職者の起こしたギャップによって、採用計画の人数と内々定を出す人数とのツジツマが合わなくなります。
最悪の場合、内々定の取り消しに発展します。
内々定の取り消しに至る、採用担当者の心理は次のようなものです。

面接のときには「すぐ入社できる」って言うから内々定を出したのに、入社まで6か月かかるんじゃ内定は出せないな…

そもそも信用できる人なのか?本当に採用していいのかな…
入社可能時期の話を発端に、信用が揺らいでいく恐れがあります。
【ポイント③】他社選考状況についての質問
他社選考状況についての質問は、次の2つの項目を確認されます。
- 【確認ポイント①】選考の進捗状況
- 【確認ポイント②】選考を受けている企業属性
質問の趣旨は、それぞれ次の通りです。
- 選考の進捗状況→選考スピードの調整のため
- 選考を受けている企業属性→自社の魅力付けの方向性を確認するため
分かりづらいかと思いますので、それぞれ説明します。
【確認ポイント①】選考の進捗状況
面接官から次のように聞かれるシーンの話です。

他社の選考状況はいかがですか?
この時、面接官は次のようなことを確認したいと考えています。

うちの採否はいつまでに出せばいいんだろう…?
つまり、自社が選考ができる期間を知りたいわけです。
なので、次の状況を簡潔に説明しましょう。
- 選考段階(応募/書類選考通過/面接/内定)
- 選考スケジュール
- 内定有無
- 内定の意思表示期限

順調です
などと答えると、コミュニケーションのボタンの掛け違いが起こります。
【確認ポイント②】選考を受けている企業属性
面接官から次のように聞かれるシーンの話です。

うちの会社以外にはどんな企業の面接を受けていますか?
この時、面接官は次のように考えています。

どんなことを話せば、うちに興味をもってくれるんだろう…?
つまり、求職者の転職軸や選社軸を確認したいわけです。
求職者が興味を持っている軸に合わせて、自社の魅力をアピールしたいと考えています。
例えば、次のような軸です。
- 業界軸
- 職種軸
- 会社規模軸
- ミッション軸
- 会社の強み軸
- 年収軸
なので、選考企業の軸からズレていない企業属性を伝えるように気を付けましょう。
なぜなら、「転職理由」とのツジツマが合わなくなるからです。
例えば、次のような状態。
選社軸:ミッション軸
⇔
転職理由:スキル軸
転職理由は「スキルを上げたい」という理由なのに、会社は「ミッション」で選んでいる状態。
となると、面接官も次のようなリアクションになります。

なんでうちを選んだの?
さらに、2つ注意点があります。
- 企業名は答えない
- ”興味”を聞かれても選社軸をブラさない
企業名を答えないのは、求職者にとってはリスクしかないから。
ごくマレに、他の選考中企業に「ネガティブな情報が提供される」という事態が発生します。
具体的には「あの求職者はやめておいた方がいい」というブラックな情報です。
もちろん、個人情報保護の観点からあってはならないことです。
ただ、そうなる前にできるリスクヘッジはしておきましょう。
沈黙は金、です。
また、面接官から次のように聞かれることがあります。

ざっくばらんに、今どんな業界・職種に興味がありますか?
オープンクエスチョンで、フランクに聞かれます。
油断して、次のように答えると、収集がつかなくなります。

興味という点では、医療業界とIT業界と人材業界です
促されるままに”興味の対象”を答えてはダメです。
あくまで、”選社軸”を聞かれていると考えましょう。
【ポイント④】機密情報に触れる質問
機密情報については、取り扱いに注意しましょう。
例えば、次のような項目です。
- 顧客情報
- 取引先情報
- 財務情報
- その他の非公開情報
配慮に欠ける場合、次のような理由で不採用になる可能性が上がります。

コンプライアンス意識が低くて、うちでトラブルを起こさないか心配…
逆に、機密情報に配慮することで、採用担当者に良い印象を与えられる可能性があります。
分かりづらいと思いますので、具体的なシーンを上げます。

現職の顧客は、うちの顧客とバッティングするところも多そうですね。
思い浮かびますか?

そうですね、確かに多そうです。

ただ、個別社名につきましては機密情報に当たってしまうので、差し控えさせていただきたいです。

そうですね!
誘導質問のようになってしまって、失礼しました。

コンプライアンス意識がしっかりした方で、安心できるな。
【ポイント⑤】質問履歴の提供
企業の質問履歴は、求職者に提供しましょう。
なぜなら、企業ごとの質問の傾向が分かるからです。
傾向が分かることで、2つのメリットがあります。
- 企業からの質問回答の準備がしやすい
- 求職者からの質問の準備がしやすくなる
情報提供を行うには、情報収集の体制が重要です。
次の社内サイクルがしっかり回っているか、チェックしましょう。
質問情報のヒアリング
↓
社内での情報集約
↓
次の求職者への情報提供
情報提供に当たっては、質問情報を頻度別に分類しておくのがおすすめです。
- 毎回の面接で必ず聞かれる質問
- 聞かれたことのある質問
なぜなら、求職者が準備の強弱がつけられるからです。
また、最近では「面接時のマスク着用」についても、事前情報があると安心です。
【ポイント⑥】回答にはPREP法を使う
PREP法とは、簡単に言えば「結論から話しましょう」という論理構成のことです。
PREPは次の頭文字になっています。
Point(結論)
Reason(理由)
Example(具体例)
Point(結論)
なぜPREP法がよいのかというと、次の2つの効果があるからです。
- 会話のすれ違いを少なくできる
- 理由の説明がコンパクトになる
会話のすれ違いがなく、コンパクトな受け答えができる求職者は採用担当者にとって好印象につながります。
ただし、PREP法を使ったことのない求職者がいきなり面接の場で使うことは難しいです。
なぜなら、日常会話でPREP法が使われることはあまりないからです。
だからこそ、面接対策の中でアドバイスを行うことが重要です。
特に、”半模擬面接”の中に取り入れ、アドバイスを行っていきましょう。

えっ!?その”半模擬面接”って何?
と思った方は、こちらの記事で詳しく解説しています。
≫【基本のき】キャリアアドバイザーが面接対策をするのに最初に抑える4つのポイント|基礎応対編
求職者側が準備する質問にキャリアアドバイザーがアドバイスする4つのポイント

質問の準備をする際は、次の4点に気を付けましょう。
- 【ポイント①】質問項目は5つ以上準備する
- 【ポイント②】条件質問を避ける
- 【ポイント③】自己アピールをしない
- 【ポイント④】”枕詞”を使う
【ポイント①】質問項目は5つ以上準備する

えっ?5つって多くない?
と感じるかもしれません。
確かに、質疑応答でできる質問の適正値は3つ位です。
なぜ5つも必要なのかというと、質疑応答時に実際聞ける質問は2つ位は”減ってしまう”からです。
つまり、次の通り。
- 求職者が準備した質問:5項目
- 面接官の説明で解決した質問:2項目
- 実際できる質問:3項目
質疑応答の前に、面接官との会話の中で次のような状態になります。

あ…考えておいた質問の答えを言われちゃった…
質問できる数は減ることを前提に、準備しておきましょう。
【ポイント②】条件質問を避ける
なぜ条件質問を避けた方がよいかというと、次の3つの理由です。
- 採用担当者にネガティブな印象を与えるから
- 質問を通じて相互理解を深めたいから
- エージェントを介しての質問でも聞けるから
なぜ採用担当者にネガティブな印象を与えるかというと、条件質問では求職者の意欲が伝わらないからです。
逆に、相互理解を深めるには、意欲が伝わる質問である必要があります。
条件質問をしてしまった場合の面接内の会話は、次のような流れになります。

営業部門の社員数は何名ですか?

5名です

ありがとうございます。

えっ!?それだけ?
それを聞いて何を知りたかったの?

本当にうちに興味あるのかな…?
逆に、意欲を伝える質問をすると、次のような流れになります。

成績上位のコンサルタントの方々に共通する、入社1年目の特徴を教えてください

先輩コンサルタントに対して図々しいまでにアウトプットをしていますね

ありがとうございます。
私も、現職では部署外の先輩営業にもフィードバックを求めにいっていました。
今まで以上にアグレッシブに取り組みたいと思います。

成果の再現性がありそうだな…
【ポイント③】自己アピール質問をしない

質疑応答で”自己アピールをしない”なんて当たり前じゃない?
と思うかもしれません。
もっと具体的に説明すると”自己アピールをしたいがための誘導質問”がNGということです。
自己アピールをしてはいけない理由は、以下の2つです。
- 採用担当者にネガティブな印象を与えるから
- 質問を通じて相互理解を深めたいから
条件質問がNGな理由と同じですね。
質疑応答で自己アピール質問をすると、”状況に合わせた発言ができない人”という印象を持たれます。
シンプルに言えば”空気が読めない人”です。
求めていないのに「いきなり商品説明をし始める営業」と同じです。
また、本来は質疑応答を通じて相互理解を深めたい。
ところが、自己アピールに時間を使うと、相互理解の機会損失が起こってしまうわけです。
具体的な会話の流れで見てみましょう。

私は営業成績トップを3年間継続してきたのですが、貴社の営業成績トップの方はどのくらいトップを継続されていますか?

確か3年ほどですかね…

わかりました。

これって自己アピールしたいがための質問だよね…

質問にはあまり意味がないな…
自己アピール質問からは、何も生まれていません。
【ポイント④】枕詞の活用
条件質問をするときは”枕詞”が重要です。
なぜなら、質問の意図が採用担当者に誤解されることを防ぐためです。
条件質問の具体例を挙げると、次のような質問項目。
- 残業
- 報酬
- 福利厚生
”単なる条件質問”は、そもそもNGです。
その中で、あえて条件質問をすると、どうなるでしょうか?
採用担当者は次のような印象を受けます。

条件質問をあえてする”特別な理由”があるんだろうな…
”聞く理由”を明確にしておかないと、採用担当者に誤解が生まれてしまいます。

え?なぜあえてそれを聞いたの?
何かネガティブな意味があるんじゃないか?
という状態です。
”聞く理由”の説明は”枕詞”を使うとスムーズです。
具体的な会話の流れでみていきましょう。

残業はどのくらいありますか?

一概には言えませんが、部署平均は月〇時間程度です。

残業はできない事情など、何かありますか?

いえ、参考に聞いてみただけで、特に事情はありません…
お互い何か「奥歯にものが挟まったような状態」になります。
この状態は選考結果によい影響を与えません。

残業については柔軟に調整可能なのですが、事前に働き方をイメージしておきたいので、参考までに繁忙期と閑散期はどのくらいあるか教えて頂けますか?

繁忙期は月10時間程度、閑散期は月5時間程度ですよ

ありがとうございます。
十分私のイメージの範囲内で無理なく働くことができそうです。
質問の意図が双方に共有されていることで、採用担当者に誤解は生まれません。
ここまで読んだあなたは、次のような悩みを抱えることはありませんか?

形式的なアドバイスはできるんだけど、求職者からの質問にその場で臨機応変に答えることができない
キャリアアドバイザーが質疑応答のアドバイスをする引き出しが少ないときの対処法

キャリアアドバイザーが質疑応答のアドバイスをするときの悩みとして、引き出しの少なさがあります。
原因は大きく分けて次の2つです。
- 面接のリアルなイメージが湧いていない
- 求人企業についての情報が足らない
対策はそれぞれ次の通り。
- 面接のリアルなイメージが湧いていない→面接同席をする
- 求人企業についての情報が足らない→リクルーティングアドバイザーとの情報共有量を増やす
【対策①】面接同席をする
リアルなアドバイスをするには、リアルな情報が必要です。
リアルな情報は、現場経験によって磨かれます。
現場経験は、面接同席によって機会を作りましょう。
最近はWEB面接も増えてきています。
キャリアアドバイザーの面接同席の機会は作りやすい状況です。
面接同席の具体的な方法は、こちらで解説しています。
≫【レア情報】転職エージェントが面接同席をする方法を5ステップで解説
【対策②】リクルーティングアドバイザーとの情報共有量を増やす
基本的な質疑応答の対策であれば、ここまでの内容を理解すれば十分です。
しかし、より深堀りした対策をするためには”求人側”の情報が必要です。
なぜなら、求人側には多くの”例外”があるからです。
例外の対応できる幅が広いほど、対策の効果は大きくなります。
求人側の情報をより多く吸収するためには、次の2つの要素が必要です。
- リクルーティングアドバイザーとの情報共有量を上げる
- 情報共有の質を上げる
情報共有量を上げるには、情報連携体制を明確にします。
つまり、日々アップデートされる企業情報が「どこに蓄積されていくか」のルールを明確にする、ということです。
情報共有の質を上げるには、より直接的なコミュニケーションをすることがポイントです。
リクルーティングアドバイザーと対面や電話等で話し、情報をハラオチするまで理解することを徹底しましょう。
文字ベースのコミュニケーションでは”感覚”の部分まで把握することは困難です。
まとめ:キャリアアドバイザー初心者でもポイントを押さえれば基本的な質疑応答対策ができる

本日のまとめをしていきます。
質疑応答の対策ポイントは大きく次の2つのポイントに分かれます。
- 企業側から受ける質問
- 求職者側が準備する質問
企業側から受ける質問への準備のポイントは、次の6つです。
- 【ポイント①】対の質問
- 【ポイント②】入社可能時期についての質問
- 【ポイント③】他社選考状況についての質問
- 【ポイント④】機密情報に触れる質問
- 【ポイント⑤】質問履歴の提供
- 【ポイント⑥】回答にはPREP法を使う
求職者側が準備する質問ポイントは、次の4つです。
- 【ポイント①】質問項目は5つ以上準備する
- 【ポイント②】条件質問を避ける
- 【ポイント③】自己アピールをしない
- 【ポイント④】”枕詞”を使う

アドバイスの引き出しが少ないな…
と感じたら、その原因と対策は次の2つ。
- 面接のリアルなイメージが湧いていない→面接同席をする
- 求人企業についての情報が足らない→リクルーティングアドバイザーとの情報共有量を増やす
ここまで読み進めることができたあなたなか、質疑応答の全体像がつかめてきたんではないでしょうか?
そうなると、次のような疑問を持ちますよね?

質疑応答を含めた面接対策の基礎を復習しておきたい
そんなあなたは、こちらの記事を読んでみてください。
≫【基本のき】キャリアアドバイザーが面接対策をするのに最初に抑える4つのポイント|基礎応対編


面接対策全体についてチェックしていきたい
という方は、こちらの記事を読んでみてください。
≫【面接通過率アップ】キャリアアドバイザーが行う面接対策3つのポイント|面接準備シートを無料公開


改めて、キャリアアドバイザー業務全体の流れも復習しておきたいな
という方は、こちらの記事を参考にしてください。
≫【成約率50%超の私が教える】キャリアアドバイザー業務のノウハウ|売上を伸ばすコツを11ステップで徹底解説
最後までご覧いただき、ありがとうございました。