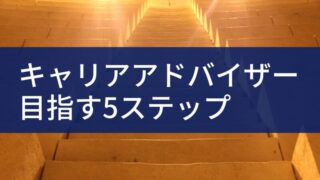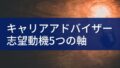キャリアアドバイザーに興味を持っているあなたには、こんな悩みがありませんか?

書類選考に通る職務経歴書の書き方を教えてほしい

どの職務経歴書フォーマットを使うのが正解?

書き終えた後の見直しって、どこに気を付ければいい?

次のような経験をもつ私たくの(@taqnock)が、あなたの悩みに答えます
- 現役の転職エージェント採用担当
- キャリアアドバイザー歴5年以上
- 未経験からキャリアアドバイザーになれた経験
WEB上には、膨大な量の職務経歴書についての情報やフォーマットがあります。
どの情報を信じていいのか。
どのフォーマットを使ったらいいのか。
迷いますよね?
この記事では、私の転職者としての実体験、採用担当者としての実体験を踏まえて、あなたの疑問に答えていきます。
- 採用担当者がどんな目線で職務経歴書を見ているのかが分かる
- 採用担当者が読みやすい職務経歴書フォーマットが分かる
- 書類選考通過の可能性を上げる職務経歴書のチェック方法が分かる
キャリアアドバイザー応募用の職務経歴書を書く7つのポイント
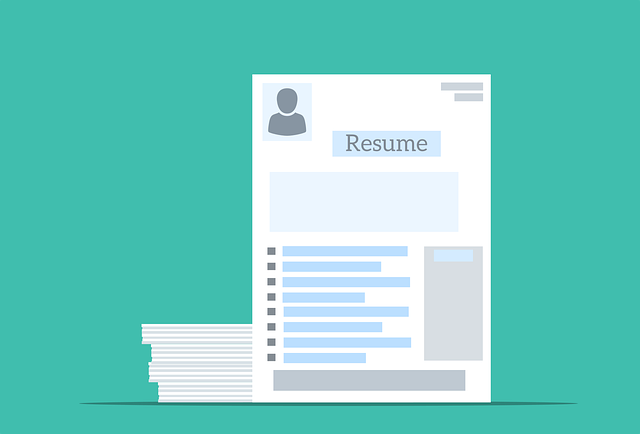
キャリアアドバイザー応募用の職務経歴書を書く7つのポイントは以下の通り。
- 実績は実数、目標達成率、順位、表彰実績の4点セット
- 職歴概要、退職理由、自己PRは入れる
- 退職理由は”他責”要素が入っていないか要注意
- 自己PRは相手目線で【ストーリーを入れよう】
- レイアウトは読みやすさ重視【最大3枚まで】
- PCスキルは業務上の利用シーンを具体的に書く
- 社内用語は使わない・専門用語は解説する
それぞれ詳しく解説していきます。
ポイント1:実績は実数、目標達成率、順位、表彰実績の4点セット
職務経歴書に実績を書くときは以下4点セットにしましょう。
- 実数
- 目標達成率
- 順位
- 表彰実績
なぜなら、採用担当者が書類選考通過の判断をしやすくなるから。
例えば、製造業と小売業では売上単価が違う。
それぞれの候補者がいたとすると、”売上実数”だけでは候補者同士の比較はできない。
つまり、採用担当者は判断ができない。
ここに、目標達成率や順位、表彰実績があることによって、判断がしやすくなる。
具体的には、次の力を判断しやすくなる。
- 目標達成率:目標完遂力
- 順位:社内での実力レベル
- 表彰実績:評価基準の理解力
ここまで読んだあなたは、次のような疑問を感じますよね?

目標を達成できていない場合も書いた方がいい?
【答え】書いた方がいい
なぜなら、書かないメリットよりも、書かないデメリットの方が大きいから。
- 書かないメリット:達成していないことを隠せる
- 書かないデメリット:情報量が少ないために不合格となる←こっちが大きい
また、自己PR欄を使えば、未達成理由や今後の展望などを補足説明することもできる。

嘘を書いてもバレない?
【答え】面接でバレる
なぜなら、面接ではその実績に至った根拠を確認されるから。
出した結果と根拠が一致していなければ、嘘はバレる。
ポイント2:職歴概要、退職理由、自己PRは入れる
職務経歴書の項目として、職歴概要、退職理由、自己PRは入れましょう。
なぜなら、採用担当者にとって、短い時間の中で、納得度の高い内容の職務経歴書を作れるから。
私もそうですが、読むのに時間のかかる職務経歴書は読みません。
読み始めた段階で不合格の判断をしてしまうことも。
「簡潔にいうと、何をしてきた人なのか?」→職歴概要
「早期離職をしなさそうか?」→退職理由
「何を考えて仕事をしてきた人なのか?」→自己PR
こういった採用担当者の基本的な疑問には、職歴概要、退職理由、自己PRを入れておくことで答えることができる。
採用担当者が早期に採否の判断をする理由は、2つの忙しさにある。
- 採用の業務は兼務であることが多い
- 書類選考は大量に行っている
ポイント3:退職理由は”他責”になっていないか要注意
退職理由は”他責”になっていないか注意しましょう。
なぜなら”他責”の退職理由は、採用担当者に”早期退職”を想起させるから。
”○○のせい”で辞める=また”○○のせい”で辞めるかもしれない
という構図が採用担当者の中で出来上がる。
具体的には「それって、結局は自分のせいなんじゃないの?」とツッコミが入る退職理由のこと。
「それは仕方ないね…」と言われるところまで、退職理由を自分自身で掘り下げましょう。
気を付けてほしいのは”一見”他責ではない退職理由。
「退職者の多い職場だから」
「ノルマの設定が非現実的だから」
「お客様のためにならないものを売らないといけないから」
確かにそれっぽい理由ではある。
しかし、本当に自分事として捉えられていたのか?
自分ができる限りの努力はできていたのか?
など、採用担当者としては腑に落ちていないことが多い。
ここまで読んだあなたは、次のような疑問を感じますよね?

ぶっちゃけ”他責”の理由で退職してしまった場合はどうしたらいい?
【答え】戦略的にぶっちゃけましょう。
後悔の残る退職や転職はよくあるもの。
私だって結構あります笑
それを無理にポジティブに言い換えようとすると”無理くり感”が滲み出る。
であれば、過去の後悔を表現した上で、現在の強い意思につなげる方が自然。
ただ、採用担当者としては、ポジティブな退職理由である方が受け取りやすいことは理解しておきましょう。
ネガティブな理由は”あえて”入れるということ。
ポイント4:自己PRは相手目線【ストーリーも入れよう】
自己PRは相手目線+ストーリーが大切。
その理由は次の通り。
- 相手目線:採用担当者が興味のないことをPRしても意味がないから
- ストーリー:結果ではないく、過程をPRすべきだから
相手目線
自己PRでは、自分が”アピールしたいこと”を書いてしまいがち。
しかし、採用担当者は、あなたが培ってきたスキルや特性を「キャリアアドバイザーとしてどう活かせるか?」という視点で見ている。
未経験でキャリアアドバイザーに挑戦するとなると、過去の経験は”活かせる部分”と”活かせない部分”に分かれる。
自己PRには、自分が”アピールしたいこと”のうち、”活かせる部分”を書いていきましょう。
相手に合わせて取捨選択をする能力が見られている。
ストーリー
既に職務経歴欄で”実績”の記載は済んでいます。
採用担当者が自己PR欄で知りたいことは、その”実績”に至るまでの過程。
実績に至った要因や努力、対応策を知りたい。
「どうもがいてきたのか」を知り、あなたの特性を理解したいと考えています。
そこで”努力の軌跡”としてのストーリーを書きましょう。
ここまで読んだあなたは、次のような疑問を感じますよね?

成果が出てなくても、書いた方がいいの?
【答え】書いた方がいい
なぜなら、採用担当者が成果の次に重視するのが、過程だから。
年齢が若ければ若いほど、成果よりも過程を重視される。
なぜなら、成果よりも過程の方が再現性が高いから。
つまり、次のように採用担当者に感じてもらえるということ。
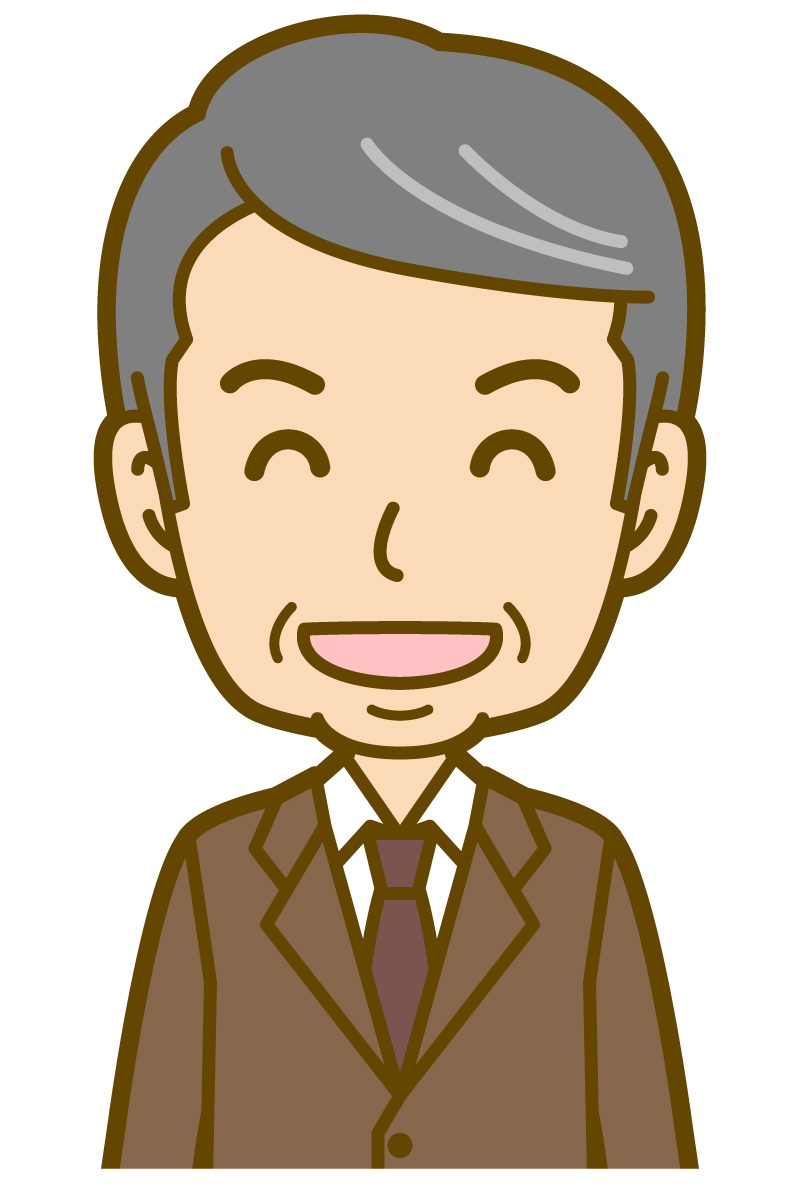
○○業界ではそのやり方では成果が出なかったかもしれないけど、キャリアアドバイザーとしては成果が出るかもしれないな
採用担当者に再現性を感じてもらうために、ストーリーは重要。
ポイント5:レイアウトは読みやすさ重視【最大3枚まで】
職務経歴書のレイアウトは”採用担当者が読みやすい”ことを最重視しましょう。
レイアウト
レイアウトについての注意点は3つ。
- 記号(■●▼など)は段落の頭で使う
- 太文字を多用しない
- アンダーラインを多用しない
記号は段落の頭に使うことで、読みやすくなる。
読みやすさが上がれば、採用担当者の印象もよくなるため、使っても問題ない。
ただし、次の2点には注意。
- 多用すると読みづらくなる
- 統一感を持って使う(中分類は”■”、小分類は”▼”などルールを決めて使う)
読みやすさを上げるために使った記号も、乱雑に使えば逆効果になる。
太文字やアンダーラインは、多用すると採用担当者が「読まされている」感覚になり、印象が悪くなる。
シンプルかつスマートに使いましょう。
枚数
職務経歴書の枚数は2~3枚が原則。
なぜなら、4枚以上になると、採用担当者の集中力が落ちるから。
シンプルに言えば、枚数が多すぎると読む気が失せる。
背景として、採用担当者は、職務経歴書と履歴書を照合しながら読み進めていることがある。
- 職務経歴書2枚なら履歴書1枚=合計3枚
- 職務経歴書3枚なら履歴書1枚=合計4枚
- 職務経歴書4枚なら履歴書1枚=合計5枚
5枚以上の書類を読み込むのは、あなたも大変だと感じませんか?
また、多くの求職者が2~3枚にまとめてくる。
その中であなただけ枚数が多い状況だと、相対的にも選考通過の可能性が落ちる。
ここまで読んだあなたは、次のような疑問を感じますよね?

職歴が多いと、枚数が多くなってしまうんだけど…
【答え】各職歴の記載量を調整しよう
全ての職歴を同じ分量でアピールしようとすると、膨大になる。
次のようにボリューム調整をしましょう。
- 活かせる職歴:ボリューム多く
- 活かせない職歴:ボリューム少なく
いずれも活かせる職務経験なのであれば、次のように考える。
- 直近の職歴:ボリューム多く
- 古い職歴:ボリューム少なく
なぜなら、古い職歴は活かせる可能性が低くなるから。
採用担当者が知りたい情報に合わせ、職務経歴書の枚数は2~3枚が無難。
ポイント6:PCスキルは業務上の利用シーンを具体的に書く
PCスキルは”どんな業務で使っていたのか”を具体的に書きましょう。
なぜなら、採用担当者にあなたのスキルイメージが沸くと加点をするから。
キャリアアドバイザーは次のような文章作成や入力作業が多い。
- 面談記録
- 案件紹介
- スカウトなど
効率的にPC作業をできないと、キャリアアドバイザー業務で成果を上げることは難しい。
そんな中、次のようなPCスキル欄の表記だと、全く経験を活かせるイメージが沸かない。
- Word
- Excel
- PowerPoint
この手のPCスキル欄はよく見かけますが、印象が良くない。
どんな業務で、どのようにPCスキルを使用していたのかを具体的に書きましょう。
ポイント7:社内用語は使わない・専門用語は解説する
社内でしか使われていない用語や専門用語をそのまま職務経歴書で使うのはNG。
なぜなら、採用担当者が理解できず、職務経歴書を読むことにフラストレーションを感じるから。
フラストレーションは選考通過の可能性を下げてしまう。
具体的にどうすればよいのかというと、次の通り。
- 社内用語:一般的な言葉を置き換える
- 専門用語:極力使わない(必要なら解説する)
専門用語の解説は、どうしても必要な場合に止め、最小限にしましょう。
なぜなら、職務経歴書は”用語解説書”ではないから。
ここまで、だいぶ解説が長くなってしまいました…。
結論、全項目に共通していることは”採用担当者目線で書く”ということ。

具体的にどんな職務経歴書フォーマットを使うのが正解?
キャリアアドバイザー応募用の職務経歴書は”逆編年体形式”を使おう

職務経歴書のフォーマットは”逆編年体形式”を使いましょう。
なぜなら、採用担当者の”知りたい順”に記載される形式だから。
つまり、書類選考通過の可能性が最も高い形式ということ。
”逆編年体形式”とは、直近の職務経歴から過去に遡って記載をしていく形式。
採用担当者としては、直近の職務経歴を最も重視する。
なぜなら、未経験者が最も転用できる可能性の高い職歴だから。
ここまで読んだあなたは、次のような疑問を感じますよね?

具体的にどのフォーマットを使ったらいいの?
【答え】大手3サイトのフォーマットを使うのが効率的
大手3サイトは次の通り。
キャリアアドバイザー求人が多く掲載されているサイトを活用する方が、効率的な転職活動ができる。
また、自己分析機能など、併せて使える機能も充実している。
≫【徹底調査】キャリアアドバイザー求人の多い転職サイト|トップ3を発表

職務経歴書を書き終えた後の見直しって、どこに気を付ければいい?
職務経歴書の見直しは自分だけじゃ不十分【転職エージェントを活用しよう】

職務経歴書の見直しは、転職エージェントに依頼しましょう。
無料で利用できます。
確かに、家族や友達に確認してもらうという方法もある。
ただ、家族や友達は職務経歴書の”形式的チェック”しかできない。
書類選考を通過するためには”採用担当者の目線”でのチェックが必要。
本の出版と似ています。
作家の原稿をそのまま出版しませんよね?
編集者という原稿を見る校正のプロがいる。
読み手の心理を想像し、より伝わるよう校正をし、世に出していく。
ここまで読んだあなたは、次のような疑問を感じますよね?

それって、ポジショントークじゃないの?
【答え】確かにその部分もある…。
私が現役の転職エージェントなのでそこは一意見として受け取ってください。
ただ、私自身が過去行った転職活動においても、転職エージェントに校正をしてもらったことで職務経歴書の質は上がった経験がある。
また、次のようなリアルな現実もある。
- 転職エージェントには、莫大な量の職務経歴書を校正したノウハウがある
- 私自身「これでは落ちるかも…」という職務経歴書の校正を行い、書類選考通過のサポートをしてきた
ただし、転職エージェントを活用するにしても”タイミング”が最重要。
せっかく活かせる経験・スキルを持っていても、進め方を間違えると結果がでないので要注意。
≫未経験でキャリアアドバイザーになるには?|11ステップと”狙い所”を解説
まとめ:キャリアドバイザー応募用の職務経歴書は7つのポイントを意識【転職サイト、転職ェージェントもフル活用しよう】

それでは、今日の内容を振り返ります。
キャリアアドバイザー応募用の職務経歴書を書く7つのポイントは以下の通り。
- 実績は実数、目標達成率、順位、表彰実績の4点セット
- 職歴概要、退職理由、自己PRは入れる
- 退職理由は”他責”要素が入っていないか要注意
- 自己PRは相手目線で【ストーリーを入れよう】
- レイアウトは読みやすさ重視【最大3枚まで】
- PCスキルは業務上の利用シーンを具体的に書く
- 社内用語は使わない・専門用語は解説する
キャリアアドバイザー応募用の職務経歴書は”逆編年体形式”を使う。
職務経歴書フォーマットは大手3サイトのものを活用する。
職務経歴書の見直しはセルフでは不十分。
転職エージェントを活用しましょう。
この時、重要なのは転職活動全体の流れ。
≫未経験でキャリアアドバイザーになるには?|11ステップと”狙い所”を解説
この記事を読んだあなたは、少しずつ理想的な職務経歴書のイメージが掴めてきているはず。
志望動機や転職理由の考え方なども参考にしながら、転職活動を進めていきましょう。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。