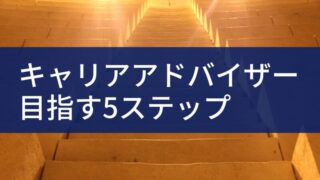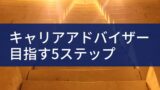キャリアアドバイザーに興味を持っているあなたには、こんな悩みがありませんか?

キャリアアドバイザーのキャリアパスってどんな種類があるの?

それぞれのキャリアパスの魅力ってどんなところ?

希望するキャリアパスを実現するにはどうしたらいい?

次のような経験をもつ私(@taqnock)が、あなたの悩みに答えます。
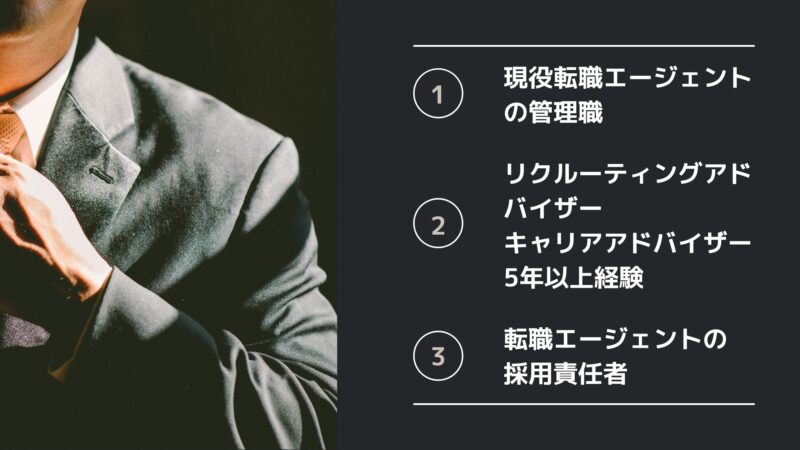
キャリアアドバイザーがどんなキャリアパスを歩むのかって、想像が付きづらいですよね?

”キャリアアドバイザー”なんだから、自分自身のキャリアについてもはっきり分かるんだろうな…
と思うかもしれません。
ただ実際のところ、自分自身のキャリアについては漠然としているキャリアアドバイザーが多いです。

日々求職者のサポートに全力を注いでいて、自分のキャリアのことにまで考えられてない…
というのが現実。
医者の不養生
なんてことわざが頭に浮かんでしまいます。
この記事では、多くのキャリアアドバイザーを育成してきた私が、様々なキャリアアドバイザーの事例を元にキャリアパスをまとめていきます。
- キャリアアドバイザーのキャリアパスを属性ごとに明確にイメージできるようになる
- 自分自身の性格と各キャリアパスの魅力を比べて、希望するキャリアパスをイメージできるようになる
- 自分の希望するキャリアパスを叶えるための準備ができるようになる
キャリアアドバイザーのキャリアパスは全部で3種類

キャリアパスとは「1社の企業内で築くキャリアの道」と定義しておきます。
3種類のキャリアパスとは、次の通り。
- 組織マネジメント
- エキスパート職
- 他部署への異動
それぞれ簡単に解説していきます。
【キャリアパス①】組織マネジメント
組織マネジメントとは”キャリアアドバイザー部門の部長”のようなイメージ。
組織マネジメントをするための具体的なステップアップの流れは、次の通り。
- 個人としての成果をだす
- チームマネジメント
- チームとしての成果を出す
- 部署マネジメント
- 部署としての成果を出す
- 部門長にステップアップ
まずは個人で成果を出さなければ、話は始まりません。
個人で成果を出した後は、任されるチームの単位が徐々に大きくなっていきます。
それぞれの単位で成果を出すには、難しさの質が違う点が苦戦するポイント。
自分で出す成果と、部門として出す成果を比べると、自分自身の役割が全く違います。
【キャリアパス②】エキスパート職
エキスパート職とは”ベテランキャリアアドバイザー”のようなイメージ。
「新人に業務を教える」というOJTはしながらも、現場でのキャリアアドバイザー業務がメイン。
エキスパート職のキャリアアドバイザーの共通点は、圧倒的に”自己一致”ができているということ。
自己一致とは、簡単にいれば”あるがままの自分”を受け入れている状態のこと。
”キャリアアドバイザー”というそれっぽい名前がついていると、多くのコンサルタントが勘違いをしてしまう。

私はキャリアのプロなんだから、しっかり指導します

私は求職者よりも業界のことに精通しています
というように、慣れが傲慢さを生んでしまう。
エキスパートのキャリアアドバイザーは違う。
上から目線ではなく、自分のキャラを活かしながら、自分にも求職者にも素直に接していく。
そうすることで、求職者が「相談したい」理由が自然と生まれます。
成約率も自然と上がっていく。
【キャリアパス③】他部署への異動
異動の一例としては、次のような部門。
- リクルーティングアドバイザー部門
- 新規営業部門
- 経理部門
- 総務部門
- 労務部門
- マーケティング部門
- 経営企画部門
ここまで読んだあなたは、次のような疑問を感じますよね?

ポジションって会社によって違うんじゃないの?
【答え】全然違う
部署構成やビジネスモデルによって、異動のパターンは全く異なります。
ビジネスモデルとしては、特に両面型か分業型かの違いが大きい。
上記はあくまで一例と考えてください。

それぞれのキャリアパスの魅力ってどんなところ?
キャリアアドバイザーの各キャリアパスの魅力を解説【種類は全く違う】

各キャリアパスの魅力は次の通り。
- 組織マネジメント=”人の多様性”の素晴らしさを実感できる
- エキスパート職=”現場の考え”を実現できる
- 他部署への異動=今までの仕事を”裏側”から見ることによる発見が多いこと
それぞれを詳しく解説していきます。
【キャリアパス①】組織マネジメントの魅力
チームをマネジメントし始めると、ある限界に気付きます。
それは「他人に”自分と全く同じこと”をさせることはできない」ということ。
なぜなら、各コンサルタントには能力的な違いや、モチベーションの違いがあるから。
つまり、自分の”分身”を作ることはできないということ。
では、どうすればいいか?
その答えは次の2つ。
- 個々人の”長所”を活かす
- 組織の業務効率を上げる
長所を活かすことで、チームに化学反応が起きます。
マネージャーが想定していなかったような成果が現れる。
”人の多様性”があるからこそ得られるもので、組織マネジメントにおける大きな魅力。
ここまで読んだあなたは、次のような疑問を感じますよね?

現場の仕事をしながら、マネジメントもするとなると激務にならない?
【答え】状況による
マネージャーの忙しさを決める要素は、次の3つが影響します。
- マネジメント業務の効率性
- マネジメント範囲
- 業務・権限委譲
この3つの要素が明確かつスムーズであれば、激務にはならない。
不明確かつ滞れば、業務が膨れ上がり、激務になりがち。
また、マネージャーにも次の2タイプがある。
- マネジメント専任型
- プレイングマネージャー
一般的にはプレイングマネージャーの方が忙しい。
なぜなら、業務量が多いから。
【キャリアパス②】エキスパート職の魅力
エキスパート職の魅力は”現場の考え”を実現できること。
なぜなら、圧倒的な実績を積んでいくと会社に与える影響度が大きくなるから。
影響度が大きくなると発言権が得られる。
発言権があれば、自分の考えを通すことができる。
逆に、入社間もないキャリアアドバイザーだとそうはならない。
せっかくの良い意見を持っていても会社から見向きもされないのが現実。
エキスパートになることで、自分の意見を実現する機会を得られる。
会社に与える影響が大きくなる具体的な理由は、売上金額が大きくなるから。
その背景は次の通り。
- 大きなクライアントを任させる=採用人数が上がる
- 重要なクライアントを任される=採用単価が上がる
過去の私も、同じく悔しい思いをしました。

〇〇をやったら、もっと会社全体の売上が上がると思うんだけどな…
と思うことが、キャリアアドバイザー時代に沢山ありました。
ただ、当時は影響力が小さく組織を動かすことができなかった。
その後、経験を積み、実績を上げることで、発言権を獲得してきました。
そして今は、多くの業務フローをより成果の出るものに変えていくことができた。
人間が想像できることは、人間が必ず実現できる
フランスの小説家ジュール・ヴェルヌ
何となく「こうなんじゃないか…」と思ったことを、自ら証明し、実現できる喜びがエキスパートにはあります。
ここまで読んだあなたは、次のような疑問を感じますよね?

会社の都合でマネジメントをさせられるってこともあるよね?
【答え】ある。ただ、その可能性を下げる方法もある。
それは、キャリアアドバイザーとしての”圧倒的な成果+マネジメント拒否宣言”をすること。
なぜなら、会社としてはキヤリアアドバイザー業務に集中させないことをリスクだと感じるから。
会社としては、高いパフォーマンスを発揮してくれるキャリアアドバイザーの存在は重要。
しかし、会社としてはできる限りノウハウを共有させたい=マネジメントさせたいと考える。
なぜなら、退職をされてしまったら大きな損失になるから。
そこで、マネジメントをさせられないほど突出した成果を上げて、マネジメントを拒否する。
我を通したいのであれば、圧倒的な成果が必要です。
【キャリアパス③】他部署への異動の魅力
他部門への異動の魅力は、今までの仕事を”裏側”から見ることによる発見が多いこと。
なぜなら、ポジションが変わることで、見る視点が変わるから。
今まで自分がしてきたい仕事は、あくまで”一部分”だったことに気付く。
全体が見えることで、自分のスキルを俯瞰し、さらに磨き上げる機会になる。

よし、もっと勉強しよう!
という気持ちを持てる、ということ。
一例としては、次のように視点が変わっていく。
- リクルーティングアドバイザー部門:求職者視点→求人者視点
- 新規営業部門:新規営業方策の多角化
- 経理部門:売上視点→コスト・利益視点
- マーケティング部門:対求職者視点→対”潜在”求職者視点
ここまで読んだあなたは、次のような疑問を感じますよね?

”異動”って言うけど、実際は”左遷”みたいなこともあるんじゃないの?
【答え】あるけど、捉え方次第
会社が異動を命じる理由は、次の3つ。
- より能力を活かせる部署がある
- 現部署では能力フィットしない
- 基礎能力が足りない
左遷になるケースは、3つ目の”基礎能力が足りない”のパターン。
会社から”使えない”と判断されてしまっている状態。
この場合は、早期に転職を考える方が賢明です。
それ以外のパターンの場合は、会社としての”ポジティブな理由”がある。
つまり、自己成長につながる機会だということ。
会社側の”異動の意図”を確認し、与えられた機会を最大限に活かしましょう。

希望するキャリアパスを実現するにはどうしたらいい?
”リスク”と”パクる”がキャリアアドバイザーのキャリアパスを実現するポイント

それぞれのキャリアパスを実現するポイントは次の通り。
- 組織マネジメント=今与えられている以上の役割を担う
- エキスパート職=トップエキスパート職の仕事の進め方をパクる
- 他部署への異動=リスク許容度と希望リターンを伝えておく
それぞれ詳しく解説していきます。
【キャリアパス①】組織マネジメントを実現するポイント
ポイントは今与えられている以上の役割を担うこと。
なぜなら、あなたを昇格させる理由が必要だから。
”理由”は次のステップで作ることができる。
- 個人として成果を出す
- チームメンバーの教育もする
- 担当チームを持つ
- チームとしての成果を出す
- 他チームの教育もする
- 部門を任される
つまり、求めるポジションを獲得するために、リスクを負うということ。
リスクを負うからこそ、リターンが得られます。
取るリスクがポジションを与える側の昇格理由になる、ということ。
【キャリアパス②】エキスパート職を実現するポイント
エキスパート職になるポイントは、トップエキスパート職の仕事の進め方をパクること。
なぜなら、成功モデルをマネするのが一番の近道だから。
具体的には、まず”行動スケジュール”からマネをしましょう。
高い成果をあげるコンサルタントは、行動の”順番”と”量”が他のコンサルタントとは違うからです。
マネをするのに見るポイントは次の3つ。
- 1か月の中でいつ、何を、どれだけやっているか
- 1週間の中で、いつ、何を、どれだけやっているか
- 1日の中で、いつ、何を、どれだけやっているか
どれが欠けても本質的に「マネしている」ことにならないので、要注意です。
同時に”成果の出る源泉”についてもマネをしましょう。
キャリアアドバイザーのエキスパート職となると、自己研鑽を行っています。
一例としては、傾聴技術やコーチング、心理学など。
エキスパート職のキャリアアドバイザーがどんなことを学び、成果につなげているのかを、直接聞いてみましょう。
【キャリアパス③】他部署への異動を実現するポイント
異動を実現するポイントは、 リスク許容度と希望リターンを伝えておくことです。
つまり、次の2つを伝えておくということ。
- リスク許容度=どういった異動なら対応できるか
- 希望リターン=異動を希望する部署、希望する報酬
なぜなら、会社側としても異動には慎重になるものだから。
下手したら退職されてしまい、貴重な戦力を失うことになります。
そんな中、次のようなキャリアアドバイザーがいたらどうでしょう?

私は異動全然OKです!
異動の話は優先的に回ってきやすくなります。
つまり、会社とWIN-WINの関係になれるということです。
リスクを取れば、リターンを得られます。
つまり、希望するキャリアパスは叶いやすくなるというわけです。
ここまで読んだあなたは、次のような疑問を感じますよね?

必ずしも、異動が自分の思い通りにならないってこともあるよね?
【答え】ならないこともある。
会社組織である以上は、自分の希望は叶わない場合もある。
しかし、叶わないことも含めて”リスク”であるということ。
つまり、リスクを取るタイミングで希望するリターンを伝えておけば、将来的に希望リターンを叶えられるタイミングが来ます。
リスクを取る以上は、臆せず希望リターンを伝えましょう。
【まとめ】キャリアアドバイザーのキャリアパスはどれを選んでも魅力的|希望を叶えるには前準備が重要

それでは、今日の内容を振り返ります。
キャリアアドバイザーの3種類のキャリアパスは、次の通り。
- 組織マネジメント
- エキスパート職
- 他部署への異動
各キャリアパスの魅力は次の通り。
- 組織マネジメント=”人の多様性”の素晴らしさを実感できる
- エキスパート職=”現場の考え”を実現できる
- 他部署への異動=今までの仕事を”裏側”から見ることによる発見が多いこと
それぞれのキャリアパスを実現するポイントは次の通り。
- 組織マネジメント=今与えられている以上の役割を担う
- エキスパート職=トップエキスパート職の仕事の進め方をパクる
- 他部署への異動=リスク許容度と希望リターンを伝えておく
この記事を読んだあなたは、きっと自分がどんなキャリアパスを歩んでいきたいかのイメージを掴めているはず。

よし、じゃあ転職活動してみよう!
と思ったあなた。
ちょっと待ってください。
転職活動は”戦略”を間違うと、大きく結果が変わります。
行動するに当たっては、次の記事を参考にしてみてください。
≫未経験でキャリアアドバイザーになるには?|5ステップと”狙い所”を解説


キャリアアドバイザーに関する基礎知識をもっと固めておきたい
というあなたは、こちらを読んでみてください。
≫【保存版】キャリアアドバイザーへの転職を目指す人のための完全ガイド
最後までご覧いただきありがとうございました。