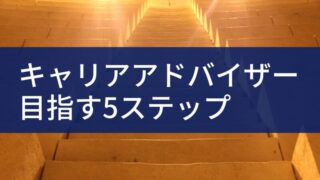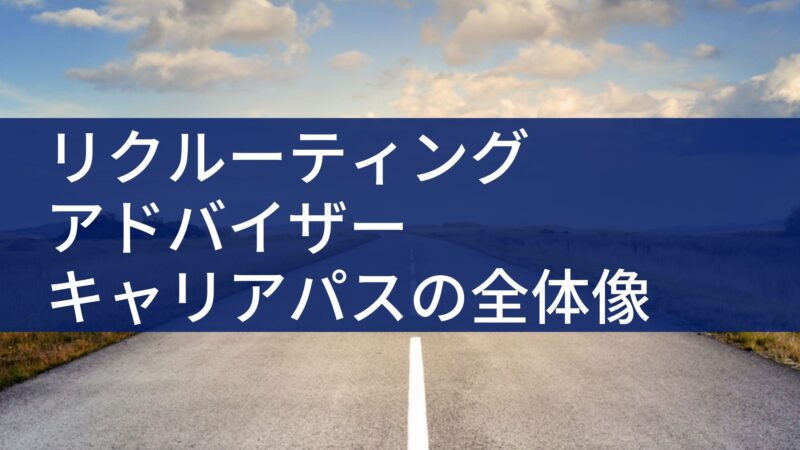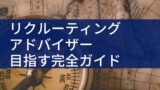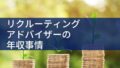人材紹介会社の営業職に興味を持っているあなたはこんな悩みがありませんか?

人材紹介会社の営業職には、どんなキャリアパスがある?

どのキャリアパスがが一番年収上がる?

キャリアパスを実現するには何をしたらいいの?

次のような経験をもつ私が、あなたの悩みに答えます。
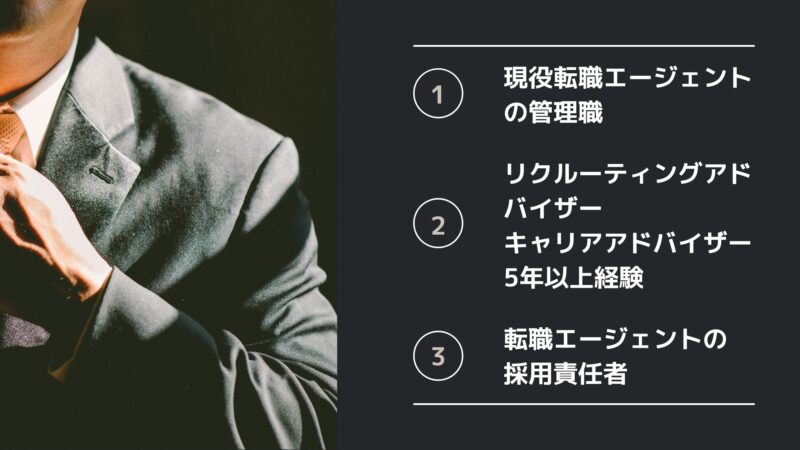
人材業界に入る前って、キャリア形成の仕方ってイメージ沸きづらいですよね?
私も業界に入る前は「営業職として頑張れば、管理職になれる」くらいしかのイメージしかありませんでした。
当時の自分に教えたいことは「社内外を問わないキャリアイメージ」を持つこと。
これを知っておけば”頑張りどころ”が分かります。
頑張りどころが分かれば、キャリアアップのスピードを上げられます。
- 人材紹介会社の営業職にとってのキャリアパスの全体像がつかめる
- 年収を最大化するキャリアパスが分かる
- 思い通りのキャリアパスをつかむ方法が分かる
リクルーティングアドバイザーではなく、キャリアアドバイザーのキャリアパスが知りたかたはこちらをどうぞ。
≫キャリアアドバイザーが歩む3つのキャリアパス【出世するには”準備”が肝】
人材紹介会社の営業職が歩むキャリアパスは3種類

人材紹介会社の営業職が歩むキャリアパスは次の3つ。
- 社内
- 社外
- 独立
私自身は”社内”と”社外”でのキャリアパスを経験しました。
社外とは、転職をして別の会社でキャリア形成をする方向性のこと。
このサイト運営を含め、現在は”半独立”の状態。
ほぼすべてのキャリアパスを経験したことになります。
そんな私の経験を元に、それぞれ詳しく解説していきます。
【キャリアパス①】社内
社内でのキャリアパスの方向性は、次の3種類。
- 営業職のマネージャー
- キャリアアドバイザーへの転向
- 他部署への異動
【方向性①】営業職のマネージャー
マネージャーへの昇進基準となる要素は、次の2つ。
- 営業成績
- 育成への関心
重要度の比率としては営業成績8:育成への関心2。
自分のマネジメントができないのに、人のマネジメントはできません。
つまり、営業成績を出せなければ、マネジメントをやる土俵に上がれない、ということ。
なぜなら、マネージャーのミッションは「成果を出す組織作り」だから。
自分が成果の出し方を知らなければ「成果を出す組織」は作れない。
一方で、「突出した成果」を出す必要はない。
つまり、標準的な成果が出せていれば問題ない。
なぜなら、マネージャーは「安定した成果」を出せる組織作りを求められるから。
つまり、組織の成果を安定させられる能力があるかを見られている、ということ。
あとは「育成への興味」があるかどうか。
現実には部下育成に興味がないのに、マネジメントをやらされるというケースはある。
ただそれは、上司にとっても部下にとっても不幸でしかない。
なぜなら、育成への興味がないチームの成果は、結局上がらないから。
この場合、お互いのために自分の志向は上司に伝えておくことが重要です。
この位ストレートに伝えた方がいい。

私は自分自身が成果を上げることをより追求していきたい

私は正直なところ部下育成にあまり興味がありません
なぜなら、ミドルマネジメントは成り手不足になりやすく、任せる側も必死に任せようとするから。
【方向性②】キャリアアドバイザーへの転向
キャリアアドバイザーへの転向基準となる要素は、次の2つ。
- 営業成績
- コミュニケーション能力
営業成績が重視されることは共通しています。
なぜなら、キャリアアドバイザーは社内で重要な立ち位置だから。
キャリアアドバイザーは求職者と最初に接点を持つ立ち位置。
そこでパフォーマンスを発揮できなければ、すべての営業工程がストップしてしまう。
だから、まず営業として一定のパフォーマンスをできる「保証」が求められます。
コミュニケーション能力を具体的に言うと、次の2つ。
- 会話のキャッチボール精度
- 顧客へのフォローアップ密度
キャリアアドバイザーの会話のキャッチボール精度が低いと、求職者の志向の捉え違いが起こる。
志向の捉え違いは、最終的に失注につながります。
顧客へのフォローアップ密度とは、次の3つの要素で構成される。
- 粘り強いフォロー
- 深いヒアリング
- 高い頻度でのコンタクト
求職者は迷い、悩みます。
キャリアアドバイザーは迷い、悩む候補者に対して密度高くフォローし、導くことが求められる。
テンプレ的な対応では成果につながらない。
なぜなら、求職者の求める価値を提供できていないから。
つまり、個別事情に合わせた高密度のフォローができるかどうかのポテンシャルを見られています。
ここまで読んだあなたは次のような疑問を感じませんか?

人材系の資格も勉強しておいた方がいんじゃないの?
【答え】リクルーティングアドバイザーとして成果を出す方が先
なぜなら、キャリアアドバイザーを任せるには、営業としての成果が前提になるから。
確かに、次のような資格は有益です。
- キャリア・コンサルタント試験
- キャリアコンサルティング技能検定
- CDA資格認定試験
- GCDF-Japan試験
ただ、キャリアアドバイザーとしての実務に役立つ部分はごく一部。
ごく一部だからこそ、キャリアアドバイザーを経験してから勉強した方が身になりやすい。
一方で「キャリアアドバイザーへの意欲を示す方法」の1つとしては効果はあります。
社内アピールの一環として有効である場合にはチャレンジしてもOKです。
【方向性③】他部署への異動
他部署への異動は、大きく分けて2つ。
- 企画系職種
- 管理系職種
企画系職種だと、次の2職種。
- 事業企画
- 経営企画
経営層に近いポジション。
営業成果、数値分析力、提案力。
総合力が求められます。
管理系職種だと、次の5職種。
- 人事
- 総務
- 労務
- 経理
- マーケティング
特に人事職の人気が高い。
人事職を目指すに当たって見られるポイントは次の4つ。
- 営業成績
- 社内への影響力
- ロジカルさ
- リファーラル実績
【チェックポイント①】営業成績
営業成績が重視されることは共通しています。
ただ、人事職の場合、少し意味合いが異なります。
例えば、採用活動のシーン。
候補者に対して自分をロールモデルの一人として語る必要がある。

私のように営業職から人事職にキャリアチェンジした成功例もあります
というように、自信をもって候補者に語り掛ける。
その自信の材料としての営業成績が必要ということ。
【チェックポイント②】社内への影響力
社内の影響力が必要な理由は、人事職は会社横断的に制度構築を行っていくから。
ハレーションが起こらないよう、現場との水面下の根回しができることが重要。
社内への影響力を大きくするには、役職者である方が有利。
まずは役職者を目指し、その後人事職にキャリアチェンジするステップがおすすめ。
併せて、社内外でMVVを語れていることも、影響力を増す材料となる。
MVVとは「ミッション・ビジョン・バリュー」。
MVVを組織浸透させることは、人事の役割の1つ。
MVVを率先して語り、役割を事前に果たすことが、役割を担う近道になる。
【チェックポイント③】ロジカルさ
ロジカルさが求められる背景は、人事は次の重要な役割を担うから。
- 社内制度設計
- 社内制度構築
- 社内制度説明
- 社内制度浸透
一連の流れを実行する基礎になるのがロジカルシンキング。
ロジカルさがなければ、制度に対する社内の不信感が増してしまう。

ロジカルシンキングって苦手です
というあなたには、次の2冊を読むことがおすすめ。
「ロジカル・シンキング」に書かれていることは、次の4つのポイントに集約されます。
2つの「論理的に思考を整理する技術」。
- MECE
- So What?/Why So?
2つの「論理的に構成する技術」。
- 並列型
- 解説型
特に「MECE」という言葉を知らない人には、本書は必ず読んでほしい。
私は本書でこの概念を知り、衝撃を受けました。

だからあの人の話には説得力があるのか!!
というリアルな気づきにつながりました。
分かりやすい話ができる人は必ず身に付けています。
また「何となくは分かっている」と「明確に意識している」の間には天と地ほどの差が生まれる概念です。
「考える技術・書く技術」に書かれていることは、ピラミッド構造による論理構成によって、自分の考えを分かりやすく伝える技術。
「ロジカル・シンキング」よりもさらに「考え方」のイメージを鮮明化させてくれます。
つまり、私が考える2冊の使い方は、次の通り。
- 「ロジカル・シンキング」:考え方の基礎を学ぶ
- 「考える技術・書く技術」 :考え方を実践できるようにする
【チェックポイント④】リファーラル実績
リファーラルとは、自分の友人や知人を自社の社員候補として紹介すること。
リファーラル実績は人事職の中でも「採用担当」としての先行投資です。
なぜなら、採用担当は採用計画人数をコミットすることを求められるから。
求められる前に計画に対して協力的であることで、一定の評価を得られる。
【キャリアパス②】転職
転職でのキャリアパスの方向性は、次の3種類。
- 同業他社
- 人材業界以外の営業職
- 元クライアントの人事職
【方向性①】同業他社
同業他社の場合、自社とは特徴の異なる転職エージェントを選択するケースが多い。
具体的には、次のような特徴の違い。
- 組織規模
- スタイル(両面型・分業型)
- 強み(総合型・特化型)
強みの部分をさらに細分化すると、次の通り。
- クライアント(業種/職種)
- 求職者(年齢層/年収帯)
- エリア
どこかの領域に強みを作っているエージェントが、特化型と呼ばれます。
また、1人のコンサルタントがリクルーティングアドバイザーもキャリアアドバイザーも行うスタイルが両面型。
どちらか一方しか担当しないスタイルが分業型と呼ばれます。
実際、どのような転職事例が多いかというと、次の2パターン。
- 総合型⇔特化型
- 両面型⇔分業型
同業他社でのキャリアパスを歩むことによって得られるメリットは、次の2つ。
- 年収アップ
- 業務の守備領域を広げられる
今現在行っている業務をベースに守備領域を広げるため、年収アップにつながりやすい。
つまり「即戦力」として採用されるわけです。
【方向性②】人材業界以外の営業職
人材業界以外の場合、強みを活かして無形商材の営業職を選択するケースが多い。
一例としては、次のような職種。
- 保険会社の営業職
- 広告会社の営業職
- IT企業の営業職
- 組織人事コンサルティング
- キャリアカウンセラー
- ハロワーク職員
- 研修講師
このキャリアパスを歩むことによって得られるメリットは、経験の横展開ができること。
今行っている業務を活かしながら、別領域の業務を経験できる。
デメリットとしては、職種によっては年収ダウンになる可能性があること。
なぜなら、業界によって年収水準が異なるから。
市場として盛り上がっている業界を選択すれば、年収維持orアップにつなげることができる。
【方向性③】元クライアントの人事職
人事職の場合、元々クライアントとして接していた会社に入社するケースが多い。
つまり、クライアントに対する日々の人材紹介業務の品質が選考対象となります。
メリットとしては、社内で実現しにくいキャリアパスを実現できること。
デメリットとしては、年収ダウンになる可能性があること。
なぜなら、他のキャリアパスに比べて活かせる経験が少ないから。
リクルーティングアドバイザーが人事職に活かせるスキルは「採用業務」の部分。
ただ、人事職にとって「採用業務」は多くある業務のうちの1つでしかない。
転職先に発揮できる価値が少なければ、それだけ年収は下がる。
ただ、元クライアントとの関係性が密接であれば、年収維持はしやすい。
【キャリアパス③】独立
独立でのキャリアパスの方向性は、次の3種類。
- 人材紹介業
- 採用代行業
- 人材紹介業向けビジネス
独立のキャリアパスのメリットは次の3つ。
- 大幅な年収アップの可能性がある
- 顧客を選ぶことができる
- 大きな裁量を持つことができる
逆に、デメリットは成果次第で年収ダウンもありうること。
【方向性①】人材紹介業
同業での独立の話は非常によく聞きます。
私自身、現職の会社の中でも何人も独立する人を見てきました。
同業独立の話をよく聞く理由は次の2つ。
- 参入障壁が低いから
- 利益率が高いから
【理由①】参入障壁が低い
資本金500万円を準備でき、免許取得ができれば、開業自体は簡単にできる。
実際、人材紹介会社の事業所数は10年で1.4倍になっている。
市場の状況について、詳しくはこちらで解説しています。
≫【2021年最新】人材紹介業界の市場規模を徹底リサーチ|今後の市場動向も予測
【理由②】利益率が高い
利益率の高さの理由は、コストがほぼ人件費と広告費のみだから。
製造業のように「原価」や「在庫」がない。
自分一人で開業するのであれば、P/L上は広告費のみしかかからない。
広告費すらかからないネットワークを作ってしまえば、コストは最小限に抑えられる。
一方、デメリットは独自性を作ることの難しさ。
言い換えれば、お客さんから選ばれる理由を作りづらいということ。

あなたの会社を選ぶ意味って何?
という状況になる。
人材紹介はリクルートを中心とした巨大企業が支配するマーケット。
「いかに大手と戦わない戦略を取れるか」が重要となる。
「リクルートとどう戦うか」を考えなくてはいけない。
なぜなら、大手の資本力、集客力は圧倒的に強いから。
将来独立するつもりなら「どの領域で戦うのか」を考えながら、日々の業務を行っていきましょう。
【方向性②】採用代行業
採用代行は、企業の人事機能のアウトソーシングを担う役割。
RPO(Recruitment Process Outsourcing)とも言われる。
具体的には、次のような業務を代行する。
- 採用人材の要件定義
- 求人情報の作成
- 求職者母集団の形成(求人媒体やスカウト代行)
- 書類選考
- 面接日時の調整
- 面接代行
- 企業説明会の企画・開催
メリットは、次の2点。
- 人材紹介会社で培ったスキルを活かせる
- ストック収入になりやすい
採用代行業は「〇か月」という単位で契約をすることが多い。
契約期間の月々の収入は確保できる。
成功報酬型の人材紹介よりも、収入面の安定性が高いと言えます。
デメリットは、次の2点。
- 需要に偏りがある
- 業務が単調になりやすい
【デメリット①】需要に偏りがある
そもそも、一定の採用人数のある企業でなければ、採用代行を利用しません。
なぜなら、自社の採用担当者で採用業務をカバーできるから。
一定以上の採用人数のある企業は「採用需要のある企業」に比べて少なくなります。
つまり、需要に偏りがあり、需要を見つけ出すことが難しいということ。
需要を捉えるためのネットワークがものを言います。
【デメリット②】業務が単調になりやすい
アウトソースするということは、企業にとって「重要度が低い」と判断した業務だということ。
重要度の低い業務を多く受注するということは、業務が単調になりやすいということ。
最初は重要度が低い業務を受注することからスタートします。
ただ、継続的に取引をすることで、重要度の高い業務まで巻き取っていく動きが重要です。
具体的には「採用要件定義」などの採用企画の部分。
クライアントと共に採用計画を練り、定義し、実行し、成功に導ければやりがいも大きい。
【方向性③】人材紹介業向けビジネス
同業向けビジネスは、幅が広い。
私もそのうちの一人。
一例としては、次の通り。
- 求職者を集めるプラットフォーム事業
- 求人を集めるプラットフォーム事業
- 業務管理ソフトを提供する事業
それぞれ具体的社名を挙げると、イメージしやすい。
- 求職者を集めるプラットフォーム事業:ビズリーチなど
- 求人を集めるプラットフォーム事業:CrowdAgentやagentbankなど
- 業務管理ソフトを提供する事業:SalesforceやHRBCなど
人材紹介会社が行う各種業務に存在する課題に対して、深堀りして解決解決の提案をしていく。
ここまで読んだあなたは、次のような疑問を感じますよね?

最初はどのステップに進むことが多いの?
【答え】営業職からスタートして、キャリアアドバイザー転向が多い。
なぜなら、必要とされる人数が最も多いから。
ここまで読んだあなたは、次のような疑問も感じますよね?

年収が一番上がるキャリアパスはどれ?
年収を最短で最大化できるキャリアパスは「人材紹介会社の営業職→独立」

独立が最も年収を上げる近道になる理由は、説明不要ですよね?
経営者と従業員のどちらが収入が高いかといえば、当然経営者。
私も今まで「社内→転職→半独立」の流れで収入を上げてきました。
一方で、独立に十分な経験が社内で積めない場合は、転職を挟みましょう。
つまり「独立の計画から逆算して、自分のキャリアを考える」ということ。

独立するのに自分に足りない経験は何だろう
そういった視点で自分の仕事を俯瞰することが、年収最大化への近道です。
「社内で十分な経験が積めない状態」とは、具体的には次のようなケース。
- 営業職の経験はできたけど、キャリアアドバイザーの経験が積めない状況
- ○○業界に対する経験をもっと積みたいけど、社内では扱わない状況
- マネジメント経験が積みたいけど、上が詰まってて昇進できない状況
会社は組織である以上、本人の希望よりも”組織の最良形”を優先します。
必ずしもあなたが組織に合わせる必要はない。
ここまで読んだあなたは、次のような疑問を感じますよね?

社内に留まるのはダメってこと?
【答え】あなたのキャリア志向に合うなら全然あり。
仕事に何を求めるかは人それぞれ。
収入よりも労働環境、収入よりもやりがいを求めている人もいます。
自分にとってベストな環境を現職で得られているのであれば、留まることも選択の1つ。
ただし”環境は変化するもの”という前提は忘れないでください。
今の環境は将来続く保証はどこにもありません。
変化した時のリスクヘッジとして、”独立”の選択肢も選べるよう準備しておきましょう。
私もその一人です。
ここまで読んだあなたは、次のような疑問も感じますよね?

希望するキャリアパスを歩むためには何をしたらいい?
人材紹介会社の営業職にとっての理想のキャリアパスを叶える2ステップ

理想のキャリアパスを叶える2ステップとは、次の通り。
- 与えられた目標を全達成する
- 上司に自分のキャリア志向を伝える
私自身、この2つをしっかり行うことで現在のポジションを獲得できました。
同時に、私以外の管理職の失敗例も多く目にしてきました。
具体的には、次のような失敗例。

ポジションは上がったけど、自分の希望するポジションじゃない……
失敗の原因は「上司に希望を伝えていなかった」ということ。
上司と部下は一蓮托生。
あなたの人事権は上司が握っていることを忘れてはいけません。
いわば、船長と船員みたいなもの。
船員の命運は船長のかじ取りにかかっています。
一方で、あなたが船長に何も希望を伝えなければ、船長はあなたが”ずっと船を漕いでいてくれる”と思います。
「船医がしたい」
「コックがしたい」
「見張りがやりたい」
と、自分の希望を伝えておくことが重要。
ただし、誰よりも船を全力で漕ぎ、船を進める貢献をすることが大前提。
伝え方のポイントは、複数の選択肢を伝えるということ。
なぜなら、組織の事情であなたの希望するキャリアを叶えられない可能性もあるから。
そういった状況の中でも、可能な限り自分の希望に近いキャリアパスとなるようリスクヘッジしておくことが重要です。
ここまで伝えたうえで、希望が叶わないなら転職を考えましょう。
ここまで読んだあなたは、次のような疑問を感じますよね?

伝えると上司から嫌がられないの?
【答え】大丈夫。
なぜなら、会社はあなたを他社に手放したくないから。
大前提として、目標達成していることが必須。
目標達成できる人材を、会社はみすみす他社に渡したくはない。
新たなポジションを用意するとき、会社はこんな期待感を持つ。

新たなポジションでも高い成果を出し、会社に貢献してくれるかも
ただし、成果を出す前から伝えすぎるのはNG。
なぜなら、上司の印象としては「離職懸念のある社員」としか映らないから。
懸念を持たれると、成果を出すチャンス自体が減ってしまう。
「成果が出る兆候が見えたタイミング」で伝え始めるのがおすすめ。
まとめ:独立するつもりで目前の目標を達成し続けることが人材紹介営業の理想的キャリアパスへの近道

それでは、内容を振り返ります。
人材紹介会社の営業職が歩むキャリアパスは、次の3種類。
- 社内
- 社外
- 独立
年収を最短で最大化できるキャリアパスは、人材紹介会社の営業職→独立。
人材紹介会社の営業職にとっての理想のキャリアパスを叶える2ステップは、次の通り。
- 与えられた目標を全達成する
- 上司に自分のキャリア志向を伝える
ここまで読んでくれたあなたは、人材紹介営業職のキャリアイメージがついたのではないでしょうか?

よし、じゃあ転職活動してみよう!
と思ったあなた。
ちょっと待ってください。
転職活動は”戦略”を間違うと、大きく結果が変わります。
行動するに当たっては、次の記事を参考にしてみてください。
≫【未経験でも大丈夫】リクルーティングアドバイザーに転職する5ステップ


リクルーティングアドバイザーに関する基礎知識をもっと固めておきたい
というあなたは、こちらを読んでみてください。
≫【サクっと分かる】人材紹介会社の営業職になるには?基礎知識~転職手順を完全ガイド
最後までご覧いただきありがとうございました。